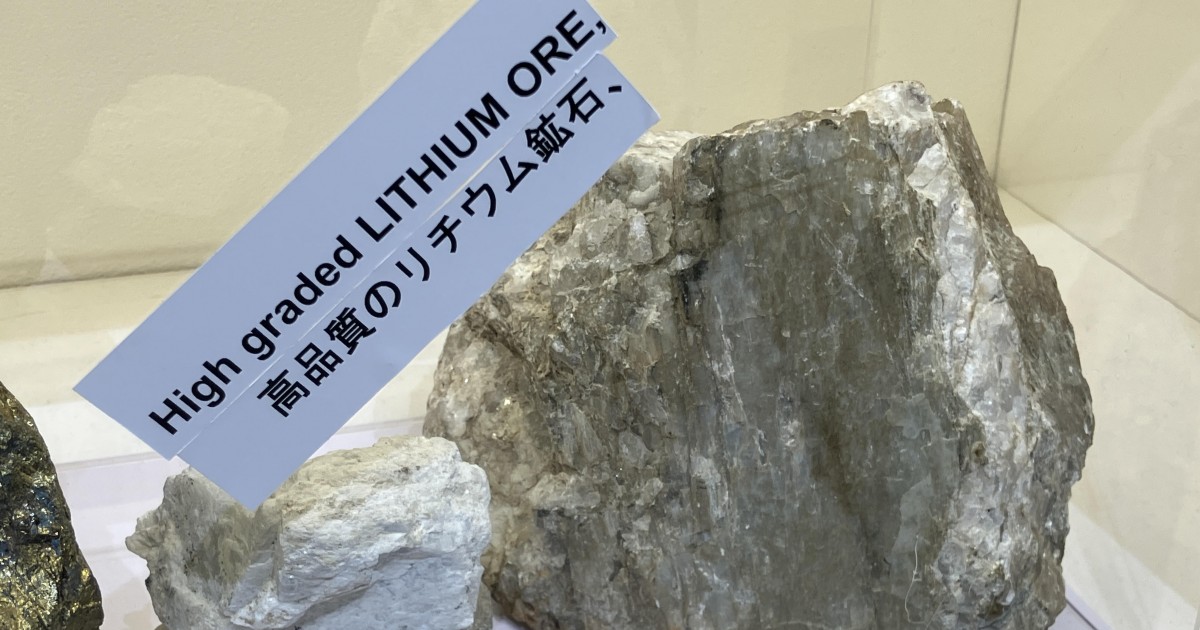双極症と人類(1)
統合失調症と人類
中井久夫先生の本に、「分裂病と人類」というのがあります(注:今は使われない病名ですが、過去の書名であるため、ご容赦下さい)。中井先生は、精神科医であると同時に、「人間とは何か」を問い続けた思想家というべき方であり、この本の中では、統合失調症を壮大な歴史の中に位置づけておられます。私もいつか、「双極症と人類」について考えてみたいものだ、と思っていました。
なぜ人類は双極症という病を抱えているのか? そこには必ず理由があるはずです。
4つの「なぜ」
そもそも、生物学において、「なぜ」を考える時に基本となる考え方が、「ティンバーゲンの4つのなぜ」として、よく知られています(長谷眞理子「生き物をめぐる4つの「なぜ」 」、集英社新書、2002年)。
1973年にノーベル医学生理学賞を受賞したニコ・ティンバーゲンは、動物の行動に対する「なぜ?」には、4つの答え方があるとしました。これは、
-
至近要因 (どのようなメカニズムか)
-
究極要因 (どのような機能があるか)
-
発達要因 (発達の中でどのように学習したか)
-
系統進化要因 (どのように進化したか)
の4つです。
以前、脳科学委員会の委員をしていた折、慶應義塾大学文学部の渡辺茂教授(当時)が、現在の脳科学の研究は、至近要因の研究ばかりで、本当の「なぜ」に答えていない。進化的視点が足りないのではないか、と指摘されました。確かにその通りだな、と思い、それ以来、進化の中で、どうしてその機能を持つ個体が選択されてきたのだろうか、と考えるようになりました。
その観点から見れば、紀元前から変わらず存在する双極症には、必ず何らかの進化的な意味があるはずなのです。特に、双極症と関連する頻度の高いゲノムバリアント(個人差)が多数見つかっていることから、こうしたバリアントが人類の中で保存されているのは、そこに何らかの適応的な意味があるからではないか、と考えることができます。
その答えは簡単に出るものではなさそうですが、まずは、実際に双極症と関連するバリアントの意味について考えてみましょう。
FADS1/2と双極症
日本人における双極症のゲノムワイド関連研究で、唯一、ゲノムワイドに関連していた唯一のゲノム領域は、FADS1/2でした (Ikeda et al, Molecular Psychiatry 2018)。
FADS1とFADS2は、どちらも、魚の油に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)などの多価不飽和脂肪酸(PUFA)の合成に関わる酵素をコードしています。

この関連は、その後欧系人でも確認され(Mullins et al, Nature Genetics 53: 817-829, 2021)、双極症のリスク因子として、最も有力な遺伝子の一つになりました。
FADS1/2については、数多くの基礎研究がなされていました。その成果から、GWASで見出された双極症のリスクを持っていると、これらの酵素の活性が低いと予想されました。
双極症のモデルマウス
そこで私たちは、両遺伝子を同時に欠損したノックアウトマウス(以下KOマウス)をゲノム編集技術を用いて作製しました。私たちもマウスも、こうした遺伝子は母方からと父方からと合わせて2つ持っているわけですが、1つずつしか持っていないマウスを作って、その行動を解析しました (Yamamoto et al, Mol Psychiatry 2023) 。
気分変動を捉えるため、マウスが好んで行う輪回し行動を半年間にわたり記録しました。その結果、このマウスは、オスでは1日中持続する、突発的な高活動を示しました。メスは、2週間程度の低活動を示しました。さらに、メスの一部は、両方を示しました。そして、メスの低活動エピソードは、リチウムにより減少しました。さらに、このマウスにDHAを食べさせると、やはりこのエピソードは減少しました。これらのデータから、私たちは、このマウスが双極症のモデルマウスになると考えました。
FADS1/2の多様性の起源
さて、ここまでだけですと、関連のメカニズム、すなわち「至近要因」について述べただけで、「系統進化要因」には答えられていません。
なぜ、双極症とFADS1/2が関連しているか? それを考えるには、このFADS1/2の遺伝的多様性が、人の進化の中で、どのように残ってきたのかを考える必要があります。